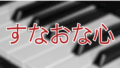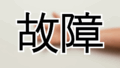はじめに
どうぞごきげんよう。
30でピアノをはじめたやつです。
ピアノ教室に通っています。
レッスンに行って帰ってきたので、その模様を書いておきます。
ピアノレッスン 3回目
ハノンの1番
メトロノーム60に合わせて弾く。
変奏7と8も弾いた。
ここで師匠より、「ハノンは4分の2拍子である」という事実が告げられる。
これまで4分の4拍子のつもりで練習していたため、「120でも余裕っすわぁ」と図に乗っていたが、実際は半分の60で弾いてるのと同じであった。
得意気に私が出していたスピードは、2歳児のとてとてダッシュだった――
師匠から「そろそろスピードを上げて練習しましょう。次は80でやります」と言われ、試しにやってみたところ、散った。
指の独立性が不足しており、3、4、5の指(中指、薬指、小指)が動かず、音がべちゃっとなる。
長期的なトレーニングで、神経をニョキニョキ通していくしかない。
ブルグミュラー2番 アラベスク
とりあえず右と左、片手ずつ弾く。
片手に集中しているときは、そこそこ表現の方も気をつけて弾ける。
しかし両手で弾くと、とたんに両方とも40点くらいに落ちる魔法がかかる。
左手は和音のスタッカートで、小気味よく音を切らねばならんが、右は右で高速5連をカマさねばならない。
右手につられ、気づけば左手の和音をスタッカートにするのを忘れている事故が多発した。
両手で弾きながら、右手の「ラシドシラ」等の5連のハキハキ感が出すのが異常に難しい。
345の指が転び、階段をズルっと踏み外したようなダサい5連に仕上がる。
また、右手の最後の音のスタッカートで力んでしまい、強く押さえてしまうクセが頻出した。
結局、一応音符通りには弾けるが、初心者あるあるの「音が転びまくる”スカスカ”アラベスク」を奏でるに留まった。
あの優しかったブルグミュラーの兄貴は、もうそこにはいなかった――
師匠曰く――
「スタッカートは、強く押すのではなく、素早く離して音を切る意識で」
「音が跳躍するときは、少し溜めろ」
「指の独立性は、なかなかすぐ身につくもんじゃねェ」
「右手9、左手1くらいの強さで弾く練習をするのもいい」
ジブリ
表現のアドバイス中心。
階段状に上がる音を、クレッシェンドで徐々に大きくするバランスが難しい。
1発目の音をデカく弾いてしまうと、後半が絶叫になる。
また、音を大きくしていこうとすると力みが入り、ギャンギャン吠えるような音になってしまう。
左手までクレッシェンドを意識しだすと、頭が沸騰し、様子がおかしくなる。
あとペダルを踏むタイミングが遅く、濁り気味との指摘が入った。
これまでなんとなくでペダルを踏んでいたが、ようやく正規のタイミングを伝授してもらった。
ありがたい。
師匠曰く――
「ペダルを踏みかえるときは、最初の音を弾いたら、それを捕まえるような意識で踏め」
「3拍子の曲は、ズン、チャッ、チャ(強、弱、弱)を意識せい」
感想
ピアノとはどうかしている楽器だと感じます。
それと、「習い事の帰り道の自転車」というエモい感情を味わっています。